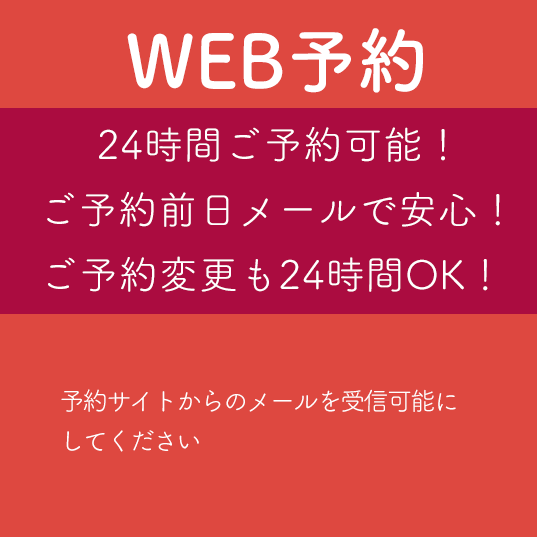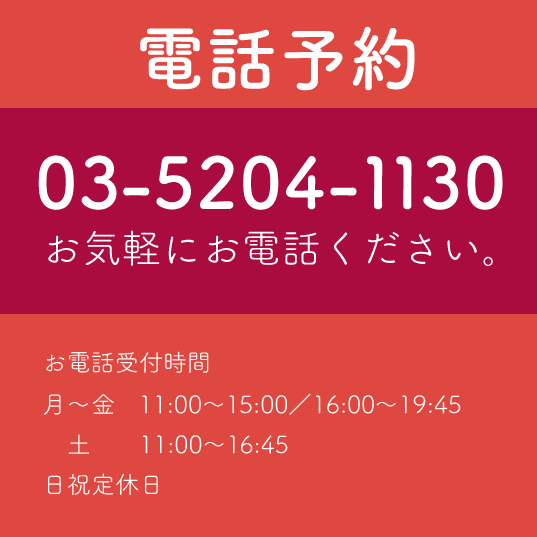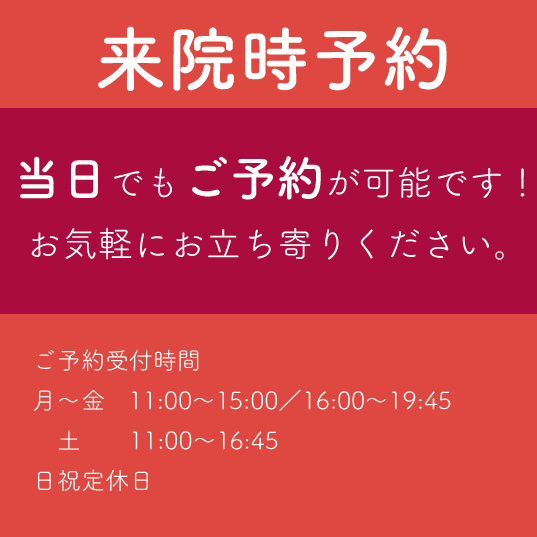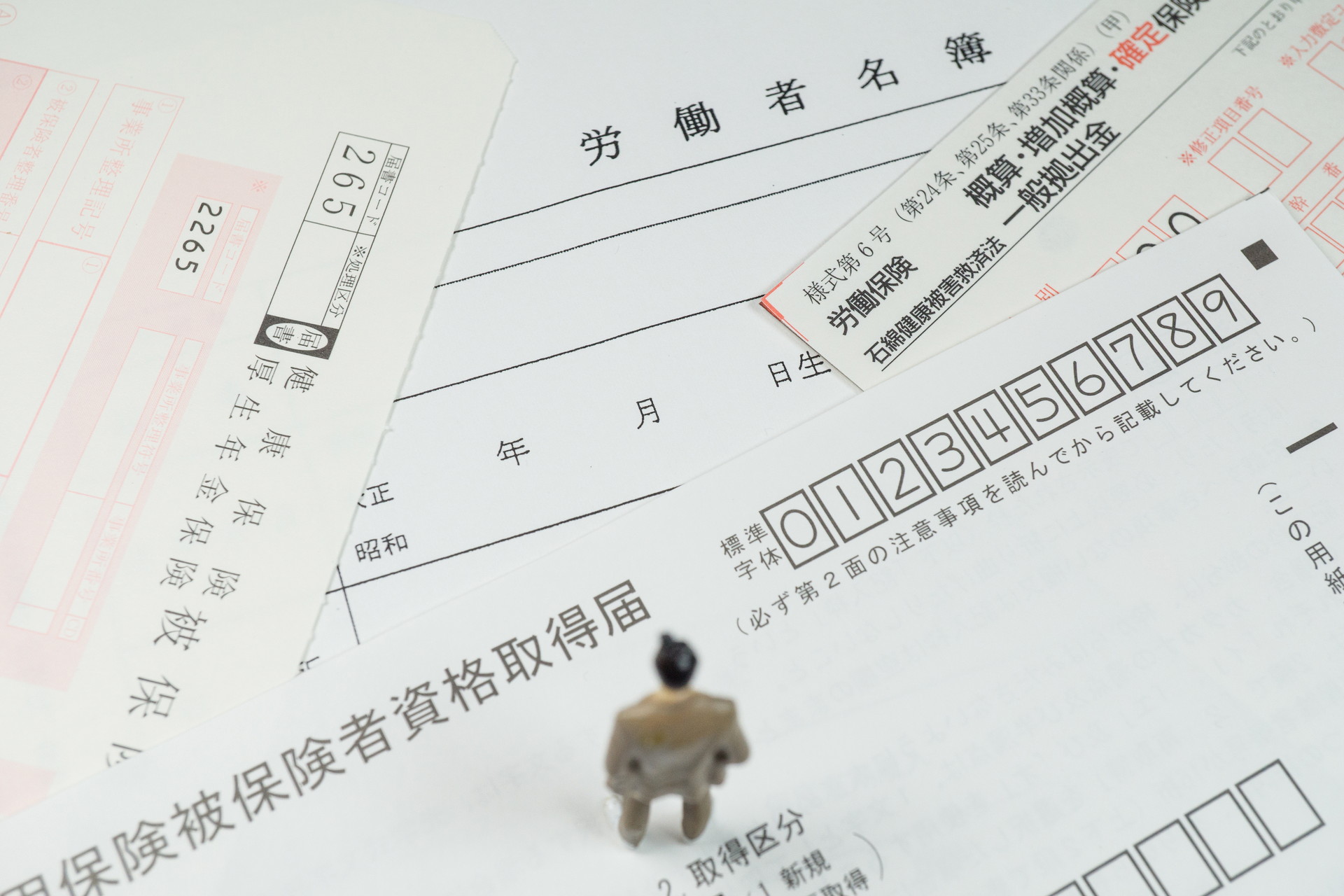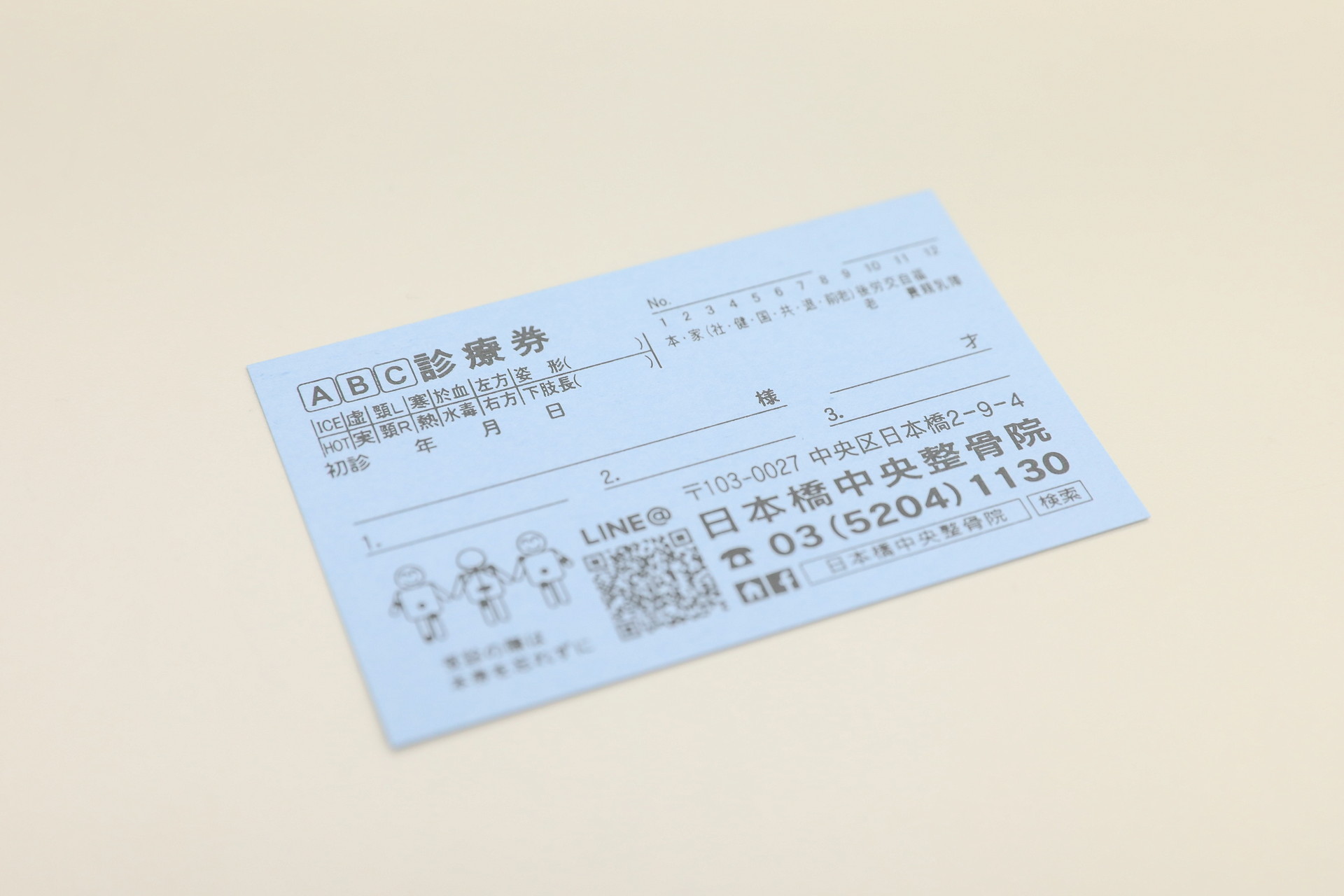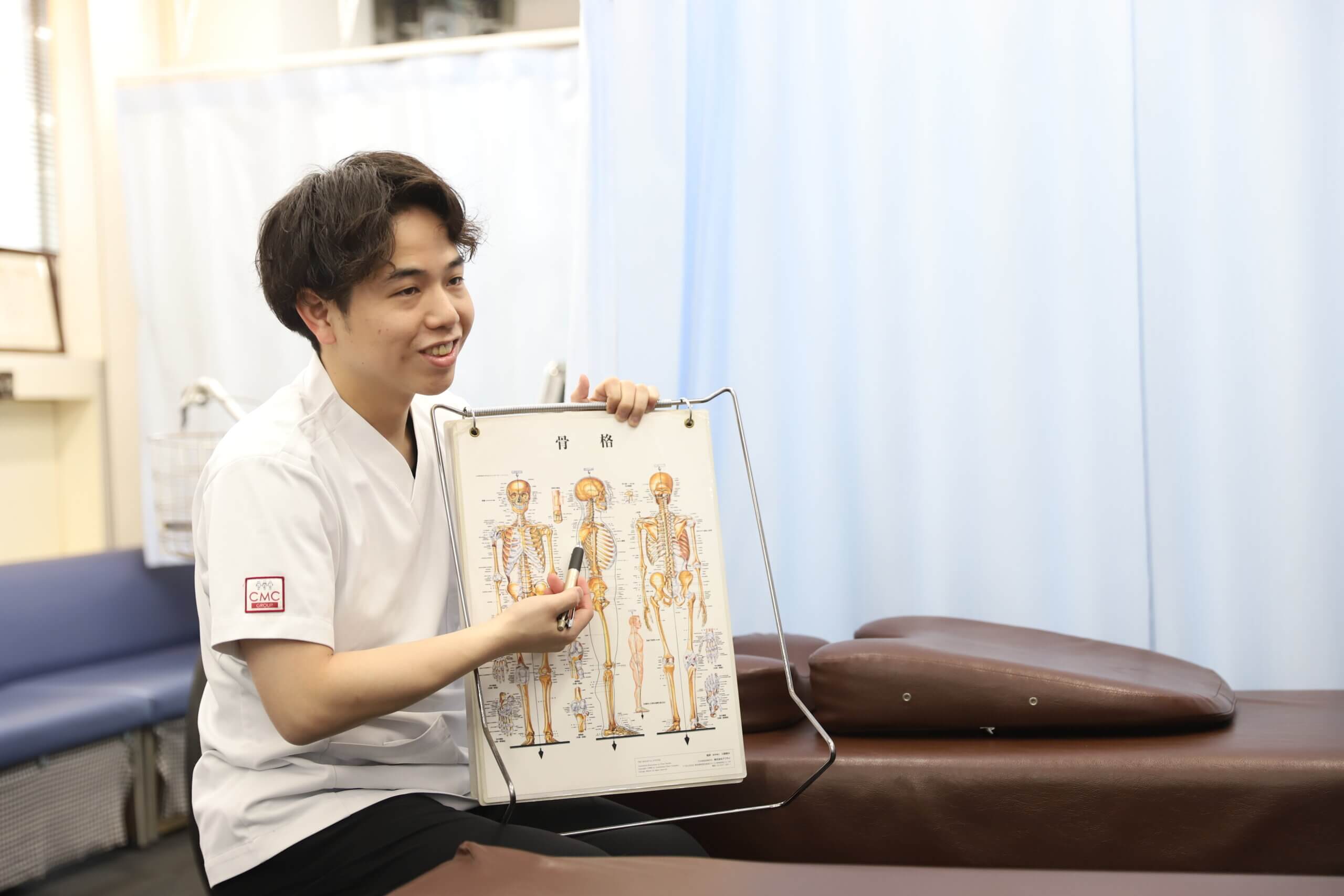
日本橋中央整骨院 からのお知らせ News
-
- 2026.2.01 ニュース 花粉症がつらい季節に。やさしく続けられる「耳ツボケア」
毎年この時期になると、くしゃみや鼻水、目のかゆみでつらいですよね。
「薬を飲むと眠くなるのが心配」「できれば自然な方法でラクになりたい」
そんな声を、患者さんからよくお聞きします。そこでご紹介したいのが、耳ツボケアです。
耳には、体のバランスを整える大切な神経が集まっていて、東洋医学では全身とつながるポイントがあると考えられています。
耳ツボをやさしく刺激することで、自律神経のバランスが整いやすくなり、花粉症のつらさを和らげるサポートが期待できます。施術はとても簡単で、1ミリほどの小さな突起物がついたシールを症状に合わせたツボに貼るだけ。
痛みもほとんどなく、副作用の心配が少ないため、お薬と併用できるのも安心ポイントです。
鼻づまりや目のかゆみはもちろん、「なんとなく不調が続く」という方にもおすすめです。耳ツボについては、花粉症だけでなくダイエットなどへの活用も含めて、動画でわかりやすく説明しています。
『耳粒?花粉?ダイエット? 耳つぼ教えます!』
ご興味のある方はぜひご覧ください!
チャンネル登録も宜しくお願いします(^^♪
-
- 2026.1.01 ニュース 食べ過ぎた年末年始…「酵素」でやさしくリセットしませんか?
あけましておめでとうございます。
年末年始、つい食べ過ぎてしまった…という方も多いのではないでしょうか。「じゃあ、しばらく何も食べなければいい?」
実はそれ、身体にはあまりおすすめできません。【無理な絶食は逆効果になることも】
まったく食べない方法は、
・栄養不足で身体が冷えやすくなる
・代謝が落ちて体調を崩しやすくなる
など、回復力を下げてしまう原因になることがあります。【おすすめは「酵素ドリンク」を使ったファスティング】
そこで当院がおすすめしているのが、
「酵素ドリンクを活用したファスティング(断食)」です。固形物を控えて内臓を休ませながら、必要な栄養はしっかり補うことで、
・胃腸の疲労回復
・老廃物の排出(デトックス)
・身体のリズムを整える
といった効果が期待できます。【酵素は、治療や回復のサポート役】
酵素は、消化・吸収・代謝など、私たちの身体を動かすために欠かせない存在です。
代謝や免疫、筋肉や骨の修復にも関わるため、酵素を補うことは、施術との相性も◎。
当院では安心してスタートできます。当院では、あなたの体調を把握したうえで、「酵素ドリンク×ファスティング」をサポートします。
当院オリジナルの「野菜果物ぎゅっと酵素(128種類の厳選素材・無添加)」を使い、普段の施術と一緒に無理なくチャレンジ可能です。【詳しくは動画でもご紹介しています】
酵素ファスティングの考え方や流れは、動画をご覧いただくと、より分かりやすくご理解いただけます。
↓ 酵素ファスティング解説動画はこちら↓
『酵素断食のプロに教わる! なぜ?何?酵素断食〜前編〜』
「ちょっと気になるな」そんなタイミングで大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください(^^♪
-
- 2025.12.01 ニュース 【12月・年末年始】受付時間の変更並びに休みのお知らせ
研修参加と年末年始のため休みをいただきます。
また、年末の最終日は営業時間を変更させていただきます。
ご不便、ご迷惑をお掛けしますがご了承の程、宜しくお願い申しあげます。年始は1/5(月)より通常通り受付いたします。
来年も宜しくお願いいたします。<受付時間変更並びに休みのお知らせ>
12/9(火) 休み(研修参加のため)
12/29(月)~1/4(日) 休み(年末年始)
1/5(月) 通常通り受付
以上です。
-
- 2025.12.01 ニュース その「治りにくさ」…実はセルライトが原因かもしれません
「なんだか最近、治りが遅い気がする…」
「むくみや冷えが、もう当たり前になってきた…」そのお悩み、もしかすると “セルライト” が体の中で悪さをしているサインかもしれません。
セルライトは、脂肪に老廃物や水分がくっついて固まったもの。
これが増えると、血流やリンパの流れが滞り、身体の回復スピードがガクッと落ちてしまうんです。【CCD(セルライトカッピングドレナージュ)ってどんなもの?】
当院のCCDは、簡単に言うと
セルライトをほぐして → 流して → めぐりを整える
という、身体の“循環”を整えるための施術です。・カップで肌を優しく吸い上げながら、固まったセルライトをゆるめる
・その後、ドレナージュで老廃物をスーッと流れる状態に整える
・特別なメディカルクリームで、さらに深部までアプローチ終わったあとは、
「足が軽い!」「ポカポカしてきた!」という声をよくいただきます。【こんな方にこそ試してほしい】
「むくみが慢性的で夕方は特にツラい」
「足先の冷えが気になる」
「最近、治療しても回復するまでに時間がかかる」
「太ってないのに、下半身が重たい感じがする」
「お尻・太ももの“ボコッ”が気になってきた」セルライトは、実は細身の方にも多いんです。
「もしかして私も?」と思ったら、一度チェックしてみてくださいね。【治療効果を高めたい方にもおすすめです】
CCDを受けていただくと、血流やリンパの流れが整いやすくなるため、
EMS・ハイボルトなど、ほかの施術の効果もさらに感じやすくなります。「もっと早く、しっかり良くなりたい」
そんな方には特に相性の良いケアですよ。CCDの流れが分かる動画があります。
「こんな感じなんだ〜」とイメージしやすいと思います。『カッピング×セルライトドレナージュ 最強のむくみケア』
ぜひチャンネル登録もお願いします(^^♪
-
- 2025.11.01 ニュース 痛み・コリ・冷えの原因かも? 肩甲骨を“はがして”スッキリ軽く!
「肩がギシギシ動かない」「背中が重たい」「なんだか肩に何か憑いているように感じる…」そんな感覚、ありませんか?
実はそれ、肩甲骨の動きが悪くなっているサインかもしれません。肩甲骨は本来、17種類もの筋肉に支えられ、自由に動く仕組みになっています。
しかし、長時間のデスクワークやスマホ操作などで姿勢が崩れると、筋肉や筋膜が硬くなって肩甲骨が背中に貼りついたような状態になります。
これがいわゆる「肩甲骨の癒着」。
血流が悪くなり、肩こり・冷え・痛み・猫背など、さまざまな不調の原因となります。次のチェックで、あなたの肩甲骨がしっかり動いているか確認してみましょう。
①両肘を胸の前で合わせて上に上げてみる
②片手で反対側の肩を押さえ、腕を上げてみる
③両手を後ろで組んで持ち上げてみる
どれか一つでも「上がらない」「痛い」「左右差がある」と感じたら、肩甲骨が固まっているかもしれません。そんなときにおすすめなのが「肩甲骨はがし」です。
固まった筋肉や筋膜を丁寧にゆるめ、肩甲骨の可動域を取り戻すことで、血流改善・姿勢改善・疲労回復が期待できます。
セルフケアでは届かない深い部分までほぐすことで、肩が軽くなり、動きがスムーズに!当院では、やさしく安心な手技で行います。
四十肩・五十肩の予防や改善にも効果的です。
気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。当院で行っている「肩甲骨はがし」を解説した動画があります。
『痛みが取れる 肩甲骨はがし』
ご興味のある方はぜひご覧ください!
チャンネル登録もよろしくお願いします!(^^♪